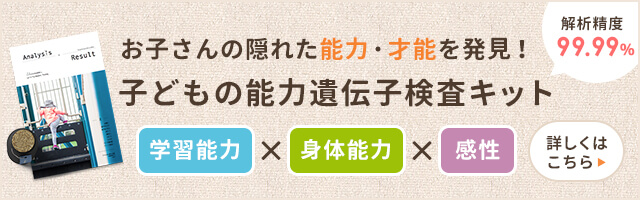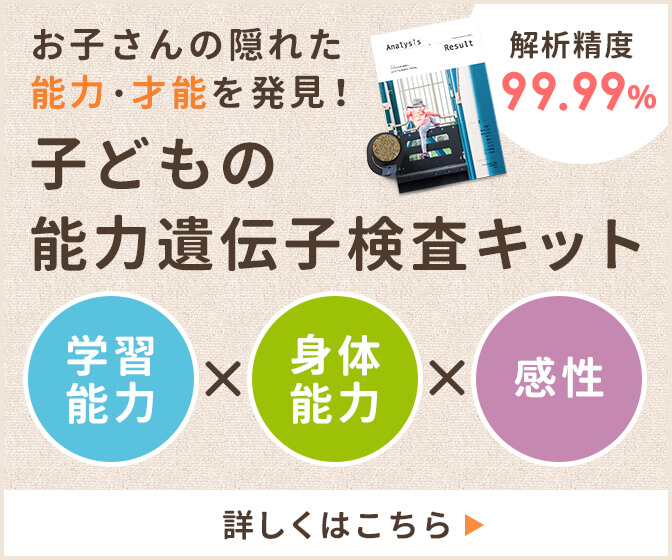こんにちは!遺伝子ママです。
最近は幼児教育・早期教育に熱心なご家庭が増え、幼いころからお子さんの才能を伸ばそうという動きがスタンダードになってきていますよね。
お子さんが将来困ることのないように、できるだけお子さんのためになることをしてあげたいというのは親として当然のこと。また幅広い年齢のお子さんに向けた教材も多く、さまざまな方法でお子さんの才能を伸ばせる環境も整ってきています。
しかし、お子さんに習い事や勉強をさせる中で、どうしても気になってしまうのがお子さんの出来不出来について。
特に習い事は同世代のお友だちと一緒に行うため、「うちの子はどうして○○ちゃんみたいにできないんだろう…」とついつい比べてしまうことはないでしょうか。
そこで今回はお子さんに得意なことがない、運動も勉強もぱっとしない…という方に向けてそんな時にどうしたら良いのか、お子さんの才能を見出す方法をまとめてみました。
悩んでいたけど誰にも相談できないという方は参考にしてみてくださいね。
運動も勉強も苦手?うちの子のよくある悩み

まずは、みなさんがお子さんについて実際にどんなことでお悩みなのかを見てみましょう。
とにかく運動が苦手で、持久走大会でもいつもビリ。体力をつけようと家でも練習していますがなかなか上達しません。
また勉強も苦手なようで、つきっきりで教えていますが成績もあまりよくないです。勉強も運動も苦手な娘と、勉強も運動も得意なお友だちを比べて「何が違うんだろう…」と落ち込んでしまいます。
【小学1年生の女の子のママ】
幼稚園から始めたスイミングとサッカーですが、後から入った子や年下の子にも抜かされています。
スイミングとサッカーだけでなく、なにをしても他の子より遅れをとっているようで見ていて心配です。私自身スポーツをやっていたこともあって、ついついいろいろなアドバイスをしてしまうのですが、息子にはあまり響いていないみたい。楽しくやっているのは事実なのですが…。
成長してもこのままだったらどうしようと不安です。
【小学1年生の男の子のママ】
このように、みなさん「勉強も運動も苦手で、他の子と比べて落ち込んでしまう」「将来が心配」と考えている方が多いようですね。
お子さんにとってよくないとわかっていてもついつい他の子と比べてしまう気持ちは誰しもが経験あるでしょう。特に幼稚園や小学校などでは他の生徒とみんな同じ、横並びの成績を求められるため、平均に少しでも足りないと不安に思うお父さん・お母さんの気持ちもよくわかります。
しかし、小さいころは他の子より遅れをとっていたけど、成長するにつれて大きく伸びていく「大器晩成」型のお子さんも意外と多いものなんです。
「大器晩成型」は意外と多いもの
たとえば有名な例では20世紀最高の物理学者であるアインシュタイン、発明王エジソン、進化論を立ち上げたダーウィンなど、みんな学校にうまく適応できなかったり、成績がよくなかったりといった子ども時代を送っています。
これはなにも著名人だけの話ではありません。子どものころは成績もパッとしなかったけど、自分のペースでゆっくり成長するにつれてどんどん伸びていき才能が開花したり、ひとつのきっかけで爆発的な成長を見せるお子さんもたくさんいます。
たとえば、小学校低学年のころはまったく体育ができなかったけど、高学年になり体がしっかりしてくるにつれてこれまでできなかったことができるようになったり、勉強がまったくできなかったけど塾に行き始めたらどんどん成績があがったり…。
サッカーやスイミングをさせていたけどいまいち伸び悩んでいて、別のスポーツをはじめたら突然才能開花!などなど、ちょっとしたきっかけがあればこれまでの悩みが嘘のように変わることもあります。
つまりお子さんが勉強も運動も苦手だからといって、あまり悲観的にとらえなくても大丈夫ということ。
だけど、今のお子さんの姿だけ見て「この子は運動も勉強もできない」と親が悲観したり、諦めてしまうと、芽生えるはずだったお子さんの可能性を狭めてしまうことになりかねませんよね。
「うちの子、勉強も運動も苦手かも…」と思ったら、心配するよりもお子さんの可能性を広げる行動を心掛けてみましょう。
お子さんの可能性を広げる行動って?

人と比べない
ついついやってしまいがちなことですが、お友だちや兄弟と比べるのはNG。
お子さんの成長ペースはお子さんそれぞれによって違いますから、小さいころはパッとしなくても、成長するにつれて伸びることもあります。お友だちや兄弟と比べて「早い」「遅い」などで心配する必要はないのです。
それに私たち大人だって、周りや兄弟と比べると嫌な気持ちになってしまいますよね。それはお子さんも同じこと。
まわりや目先のことにとらわれずに、お子さん自身の成長に目を向けて長い目で見てあげましょう。
強制するのではなく見守る
勉強や運動ができないときに「どうしてできないの」「もっと練習しなさい」と強制してしまうことはありませんか?
でもこの言葉はお子さんにとって、「がんばっている自分」や「できない自分」を否定されているように感じてしまう言葉です。
それに、この言葉を言ってしまう大人の大半はイライラしています。そのイライラはお子さんにも必ず伝わりますし、自信をなくさせてしまう原因にもなるでしょう。
自信が無くなってしまうと自己肯定感が低くなり、新しいことにチャレンジする意欲や、ものごとを始めるためのやる気までなくなってしまいます。
なにより、自分が一番信頼しているお父さん・お母さんに否定されるのはお子さんにとっても辛いものです。
「どうしてできないの!?」と言ってしまいたくなることもあるかもしれませんが、そんなときはぐっとこらえ、お子さんを見守ってあげるようにしてください。
「できない」よりも「できる」に目を向ける
「勉強も運動もできない」ばかりに気をとられて、お子さんのできるを見逃していませんか?
お父さん・お母さんがお子さんの「できない」ばかりに目を向けていると、お子さん自身も「自分はできない、ダメだ」と思うようになってしまいます。こうなってしまうと自信を取り戻すのは大変です。
そうなる前にお子さんの「できない」や「苦手」ではなく、お子さんが夢中になって取り組んでいること、得意なことや、お子さん自身の強みを見つけてほめてあげましょう。
お子さんのできるに目を向けて褒めてあげることで、得意なことをもっと伸ばしたり、苦手なことがあっても「この子はこれが苦手だからしょうがない」と広い心で見守ることができます。
ぜひほめ上手になってお子さん自身の強みを伸ばしていきましょう。
以上が、お子さんの可能性を広げるための行動まとめでした。
うちの子、運動も勉強もできないかも…と思ったら、ちょっと落ち着いてお子さんの良いところに目を向けてあげてくださいね。