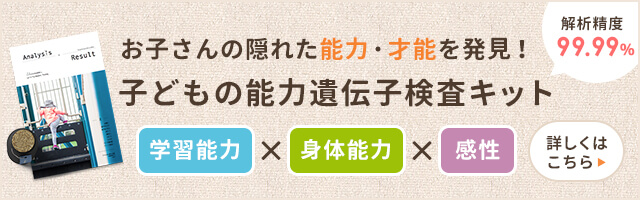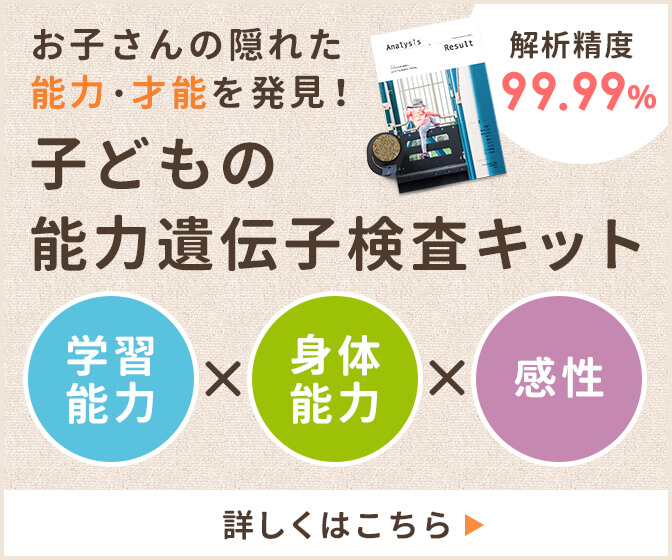こんにちは!遺伝子ママです。
今年は新型コロナウィルスの影響でなかなか従来の新学期がスタートできない状況ですが、本来ならばお子さんたちの新学期が始まり、新しいクラスにもなじんできている頃だと思います。
新学期の始まりは新しいお友だちとの出会いや、これまでとは違った環境になりますので「新しいクラスになってお友だちと仲良くできているかな?」と毎日ドキドキしているお父さん・お母さんも多いのではないでしょうか。
親としては、お子さんにはできるだけたくさんお友だちを作って楽しい学校生活を送ってほしいと願うものですよね。
しかし、比較的どのお友だちでも仲良くできる子もいれば、お友だち作りが苦手な子もいると思います。そんなとき、親としてどう声を掛けたら良いのか、何をしてあげたらいいのか悩んでいる方もいるのでは?
そこで今回はお子さんのお友だち作りのヒントをまとめてみました。お子さんに楽しく新学期を始めてほしい!と思っているお父さん・お母さんは参考にしてみてくださいね。
お友だち作りが苦手なタイプってどんな子?

お友だち作りが苦手なお子さんは、大きく分けて4つのタイプに分けることができます。
引っ込み思案で受け身タイプ
恥ずかしがり屋なお子さんや、引っ込み思案なお子さんは自分からなかなか声を掛けたりすることができません。
そのため、お友だちから声をかけてもらうのを待つ「受け身」になってしまうので、最初の友だち作りでつまづいてしまう場合があります。また、友達の輪に入れても自分の気持ちを言葉にできないことも多いです。
集団でワイワイするのが苦手タイプ
二人や数人程度のグループだと問題ありませんが、たくさんの人がいるところだと話すタイミングがわからなくなったり、委縮してしまうお子さんもいます。
最初のお友だち作りは比較的スムーズにできますが、複数のグループで集まるのが苦手なのでお友だちが増えるにつれ自然と離れてしまったり、自分の気持ちが言えなくなってしまうこともあるようです。
一人が好きなタイプ
親としては心配になってしまうかもしれませんが、お友だちと一緒にいるより一人が好きなタイプももちろんいます。
このタイプのお子さんには無理にお友だちを作らせるよりも、本人のペースに合わせて好きに過ごさせる方が良いでしょう。多くの場合、本人が熱中できる趣味をもっていることも多いので、あまり心配せずにお子さんが好きなことを存分にさせてあげてください。
それに、本当に気の合う友達に出会ったときには自然と仲良くなることができるものです。その時が来るまで見守ってあげましょう。
わがまま・乱暴な言葉遣いタイプも…
お友だち作りが苦手なお子さんには、度を過ぎたわがままだったり、乱暴な言葉遣いをしてしまうためお友だちができない…という子もいます。
みんなと一緒に遊ぼうとしているのに「○○じゃないといや」「○○はダメ」など自己中心的な発言が多いと、お友だちができても仲間はずれにされてしまうことも。
また、おうちでも「いやだ」「きらい」など、ネガティブな言葉が多いような場合、学校でもお友だちに言ってしまっている可能性がありますので、注意深く観察して注意してあげてください。
以上が、お友だち作りが苦手なお子さんの4つのタイプでした。
なかには本人のちょっとした努力で解決できることもありますが、親としてできることは、無理やりお子さんにお友だち作りをさせようとしないこと。
それよりも、お子さんがどうしたいのか気持ちを聞いてあげて共感してあげることや、ちょっとした手助けをしてあげることが大切です。
また、ご紹介したようにお子さんによってはお友だち作りよりも大切なものを持っていることもあるので、お子さんがどのタイプなのか見極めつつ見守ってあげると良いでしょう。
では最後に、お友だちが欲しいけどうまくいかないというお子さんのためにちょっとしたお友だち作りのコツをご紹介します。
子どもの友達作りのコツ

自分から積極的に話しかける
基本的なことですが、自分から話しかける勇気を持つことが大切です。
多くの人は自分に興味を持ってくれたり、好意を持って話しかけてくれる人には良い印象を持ちますので、自分で積極的に話しかけることができればお友だち作りがスムーズにできるでしょう。
特に新学期は、知らないお友だちばかりが集まるのでみんな緊張しています。まずは「おはよう」「バイバイ」などの挨拶から初めて、「一緒に遊ぼう」「隣に座っていい?」など、簡単なことでいいのでどんどん話しかけていきましょう。
もしも幼稚園のお子さんの場合は、お父さん・お母さんから「○○ちゃん、●●と一緒に遊んでくれる?」と助け船を出してあげるのも良いかもしれません。何度か繰り返していくうちに、自然とお友だちになれることもあるでしょう。
好きなものが一緒の子をみつける
やみくもにお友だちを作ろうとせずに、好きなスポーツや漫画、テレビなど共通の話題を持つお友だちを見つけることも大切です。
自分が興味のあることを共有できる相手とは仲良くなれる可能性が高いですし、一緒に遊ぶきっかけにもなります。そういった意味では、クラブ活動や習い事を始めてみるのも良いかもしれませんね。
親同士が仲良くなるのも効果的
まだお子さんが幼い場合は、たまたま同じ病院だったり公園で出会ったり、お父さん・お母さん同士がまず仲良くなる場合も多いですよね。
お父さん・お母さん同士が家族で遊ぶようになると、自然とお子さん同士も仲良くなりますし、一緒に遊んだりができるようになります。また、お子さん同士でトラブルがあった場合も、お父さん・お母さんが把握しやすくなるというメリットもあるでしょう。
保護者同士のコミュニケーションをついついおろそかにしてしまう方もいるかもしれませんが、お父さん・お母さん同士が仲良くしている姿を見ることはお子さんにとっても良いことですので、まずはお父さん・お母さんが積極的にお友だち作りをしてみるのもいいかもしれませんね。
以上がお友だち作りのコツでした。
友だち作りは難しいと考えてしまいがちですが、基本はとてもシンプル。あまり重く考えすぎずに「気が合ったら一緒に遊べばいいや」くらいの気持ちでチャレンジしてみましょう。