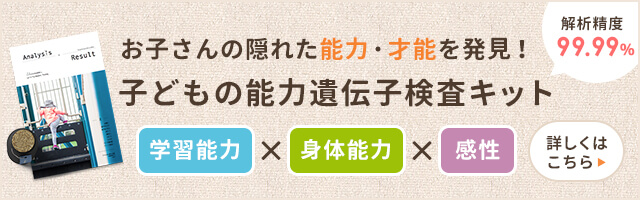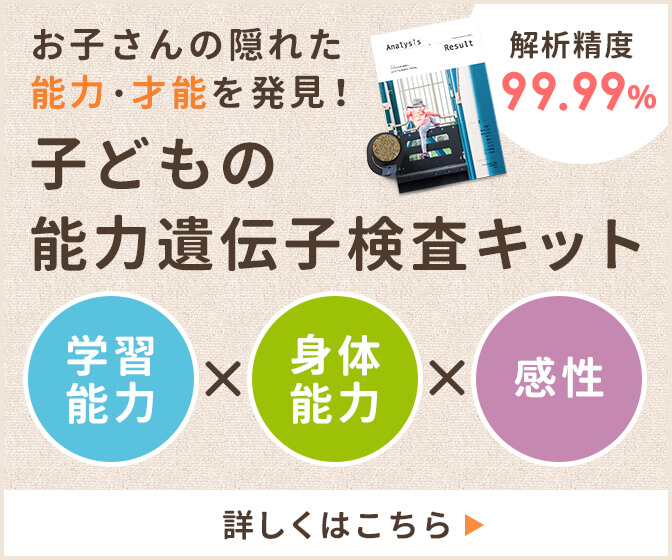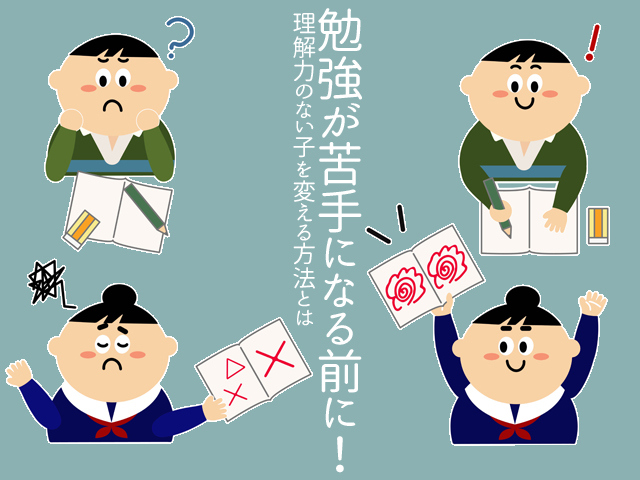
こんにちは!遺伝子ママです。
新型コロナウイルス流行に伴いお子さんが休校になった、自宅待機をしているというご家庭も多いと思いますが、みなさんお子さんの「勉強」どうしていますか?
小学校がおやすみの間はお父さん・お母さんがお子さんの勉強や宿題を見なければなりませんよね。久しぶりの勉強に四苦八苦している方も多いと思います。
しかしお子さんが勉強や宿題をうまく進められなかったり、思ったよりもできていなかったり、「もしかしてうちの子、理解力がないのかも…」と不安になってしまった方もいるのではないでしょうか。
理解力がないと宿題を読み解くだけでも一苦労ですし、将来的に勉強嫌いになってしまう可能性もありますから、早めに対処してあげたいですよね。
そこで今回は勉強嫌いになる前に、お子さんの理解力を高める方法についてまとめてみました。
お子さんの勉強について不安を感じていた方は参考にしてみてくださいね。
理解力がない子の特徴

まずは「理解力がない子」とはどんな子なのか特徴をご紹介します。
話を聞けない
理解力が無い子の最大の特徴は「人の話を聞けない」ことです。
よくあるパターンとしては、お父さん・お母さんの「わかった?」という問いかけに「わかった!」と元気よく答えるだけで、また同じ失敗をしてしまったり何を言われているか理解していなかった…というもの。
これはお子さんにとって「説明の意味がわかった」だけで止まってしまっているため、実際に自分がしなければならないことは何なのかまできちんと確認する必要があります。
集中力がない
小学校の授業時間はだいたい45分前後ですが、集中力がないと授業以外のことに気を取られたり、じっと座っていられなかったりと勉強どころの話ではなくなってしまいます。
ご自宅での勉強においても、1時間だらだらしながらするのと30分しっかり集中してするのとでは覚え方も変わってきます。
集中力がないと理解力をあげる基礎ができていないことになりますので、小さいころから少しずつ習慣づけてあげなければいけません。
柔軟な考えが苦手
過去の経験や一度教わったやり方などにとらわれてしまいがちで、柔軟な考えが苦手なのも理解力がない子の特徴です。
そのため自分の知っているルールに当てはまらない意見を受け入れられなかったり、いつもと違う事態になったときにパニックになってしまいます。
またたとえ話が苦手で、たとえの言葉通りに受け止めてしまったり、本質ではないところが気になってしまい話が進まなくなってしまうこともあるようです。
質問と答えがかみ合わない
理解力のない子は、なにを聞かれているかを正しく認識することができません。聞いていることとは違うことを答えたり、言葉が足りていなかったりします。
また人の話を聞くのが苦手なので、質問する側になったときに相手の答えを無視して自分の話ばかりすることも。これはお友だちとのトラブルにもなりかねませんので注意しなければなりませ
ん。
以上が、理解力がない子の特徴でした。
もちろん理解力がないからといってすべてがダメというわけではありませんし、努力次第で伸びる子も多いでしょう。しかし、将来的に学力を伸ばしたい、勉強嫌いにさせたくないという方は早いうちから理解力を高める対策を取りたいですよね。
実はお子さんの理解力は、特別な何かをしなくてもお父さん・お母さんとの会話の中で鍛えることができるのをご存知でしょうか?そこで次はお子さんの理解力を高めるための方法をいくつかご紹介したいと思います。
理解力をつけるための方法

子どもの話をしっかり聞く
お子さんの理解力をあげるためには、まず人の話を聞くことを覚えなければいけません。そのためには、お子さんの話をしっかり聞いてあげることが大切です。
人の話を聞く練習なのに、なんで話を聞いてあげなければいけないの?と思うかもしれませんね。これは、お子さんの話をさえぎらずに聞くことで話を聞いてもらえた満足感をお子さんが感じるため。
お子さんが話している途中で話をさえぎってしまうと、お子さんは「早く話さないと聞いてもらえない」と思うようになってしまい、結果相手の話をさえぎって話したり自分の話ばかりするようになります。
そうならないように、まずはお子さんの話をしっかりきいてあげましょう。
声かけで語彙力アップ
お子さんへの声かけは理解力と一緒に語彙力も高める効果があります。
たとえば「今日は学校で何をしたの?」という質問だけでも、理解力がない子はどう答えたらいいかわからないとなってしまいがち。
そのため「誰とどんなことをして遊んだのか」「1日楽しかったのか」「どんな勉強をしたのか」など、問いかけの目的をはっきりするだけでもとても答えやすくなります。
質問を細かくして、ひとつひとつ整理しながらお子さんに話をさせることも理解力を高める練習のひとつ。これを繰り返していけば、お子さんも自然と自分の気持ちを上手に話すことができるようになるでしょう。
アウトプット
これは普段の会話だけでなく勉強でもできることですが、お子さんに言い聞かせたり教えたことを「お子さん自身の口で表現させる」ことも大切です。
「わかる、理解する」ことは、ただ耳で聞いただけでは不十分。お子さんが一度聞いたことを、自分の力で書いたり話したり「アウトプットする」ことで理解につながります。
文章を音読したり、漢字の書き取りを繰り返すこともアウトプットのひとつ。また、「お母さんが今言ったことを説明してみて」等で促してあげると、お子さんは自分の力で考えながら話そうとします。
「本当にわかっているのかな?」と思ったらこの方法を試してみてください。
以上が、理解力をつけるための方法でした。
普段の会話をちょっと工夫するだけでお子さんの理解力をぐっと成長させることができますので是非試してみてくださいね。