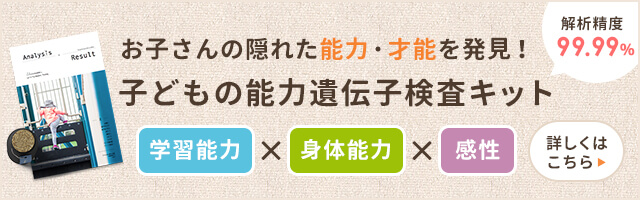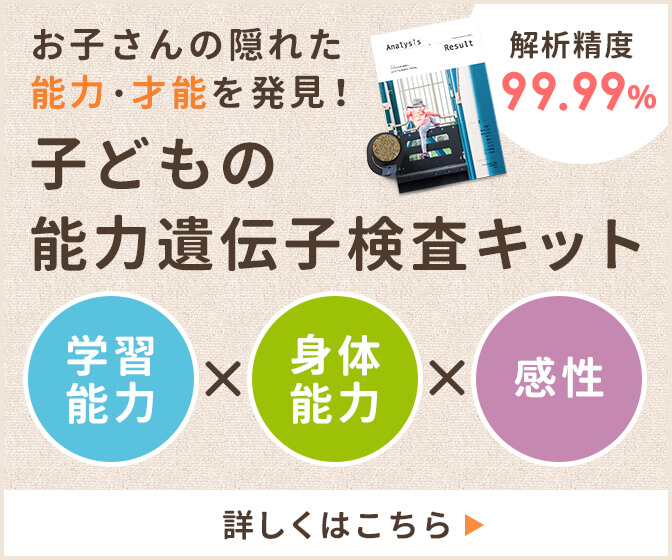こんにちは!遺伝子ママです。
お父さん・お母さんの中には、なるべく早くお子さんの才能を開花させてあげたい!と早期教育・幼児教育にとりくんでいる方も多いと思います。
特に自粛期間中の今、ご家庭での勉強をどうするかはとても大切な時期ですよね。
しかし、いつごろまでにどんな勉強をさせたらいいのかわからない…、あまり無理に勉強させて逆効果になったらどうしよう、と思っている方もいると思います。
そこで今回は小学校入学前のお子さんを対象に、いつから勉強をスタートして、どんなことをさせたらいいのかをまとめてみました。
早期教育・幼児教育に興味を持っていた方は参考にしてみてくださいね。
小学生になる前に身に着けておきたいこと

多くの場合お子さんが本格的な「勉強」を始めるタイミングは、義務教育である小学校からですよね。
しかし、勉強は小学校で教えてもらえるから家で勉強させなくても大丈夫、と考えるご家庭は少ないでしょう。
なぜなら小学校では1クラスにいる約30人のお子さんたちをいっぺんに指導しなければならず、授業も限られた時間の中で進めなければなりません。たとえばクラスの中で一人だけ文字が書けない子がいても、その子に合わせて授業しましょう…とはならないのが現状です。
そのため、勉強の基本的なことは小学校に通う前にある程度身に着けておく必要があります。では、勉強の基本とはなんでしょうか?
「勉強習慣」を身につけよう
小学校に上がる前に身に着けておきたい勉強の基本は、まず「勉強習慣」をつけるということです。
小学校に上がったばかりのお子さんは、新しい友達に新しい場所と、これまでとは全く違う環境になります。
特に授業ではだいたい45分前後の間机に座っていなければなりません。勉強習慣のないお子さんだと、慣れない環境でおとなしく座っていられず立ち上がったり落ち着きがなかったりといった勝手な行動をとってしまう可能性があります。
そうなると他のお子さんも授業が進められませんし、勉強どころの話ではないですよね。
この机に向かうことは幼稚園でも行いますので、年少さんのころから少しずつ習慣付けてあげることが大切。まずは5分くらいの短い時間から始めてみて、小学校に入る前に机に向かって勉強をする習慣ができるようにしてあげてください。
小学校に入る前に20から30分間ほど集中力が続くようになれば、授業も問題なく受けることができるでしょう。
ひらがな、数字の読み書きを覚えよう
勉強習慣をつけることと一緒に、ひらがなや数字の読み書きも覚えておいたほうがいいことのひとつ。
小学校ではお父さん・お母さんが付き添えませんから、お子さんが自分の机や下駄箱の場所、授業を受ける時間や教室を自分で探さなければなりません。そんな時に自分の名前や教室の名前が読めないと困りますよね。
もちろん小学校でもひらがな、数字の読み書きを勉強しますが、ほとんどのお子さんは文字の読み書きができる状態で入学してくるのです。慣れない環境で1から覚えるよりも、ご自宅でお父さん・お母さんと一緒に覚えた方がお子さんも楽しく勉強できます。
まずはえんぴつの持ち方からはじめてみて、簡単なドリルなどをつかって少しずつ覚えていきましょう。ひらがなを読む練習は絵本の読み聞かせをしながらでもできますので、お子さんが興味をもったことから関連付けて始めると良いですね。
以上が、小学校に上がる前に身に着けておきたい2つのことでした。どちらも年少さんから少しずつ進めていけることなので、幼稚園にあがるのと同時にスタートするとその後の勉強がスムーズにいくようになるでしょう。
また、お子さんがまだ小さいうちに大切なのは「勉強をさせよう」と気負うことではなく、お子さんが興味を持ったことからじょじょに慣れさせていくことです。あまり無理に勉強させようとして、将来勉強嫌いになってしまうのは避けたいですよね。
そこで最後に、将来勉強嫌いにさせないためにお父さん・お母さんが気をつけたいことについても合わせてみていきましょう。
勉強嫌いにさせないために!気をつけたいこと

「つめこみ教育」をしない
まだ小さいお子さんは集中力もそんなに続くものではありません。早く覚えさせたいからと長い時間勉強させたり、勉強しないと遊ばせないなど強制させることはやめましょう。
長い時間勉強させるとお子さんも飽きてしまいますし、勉強=いやなものと思ってしまいます。まずは5分など短い時間から始めて、お子さんが楽しい!と思える程度の勉強量だけさせましょう。
逆に、お子さん自身が興味をもって「知りたい!」と感じたことはどんどん学ばせてあげるといいですね。なんでも質問されるとお父さん・お母さんもうんざりしてしまうかもしれませんが、おおらかな気持ちで答えてあげましょう。
間違いを指摘するのではなく褒める
お子さんが勉強をしているときに、ついつい文字の書き順などが間違っていると指摘したくなるかもしれません。しかしあまり細かいところまで指摘されるとお子さんは「がんばったのに褒めてもらえなかった」と感じてしまいます。
まずは上手にできた点を見つけて褒めてあげることが大切です。
親子で楽しめるやさしい問題から始める
勉強に熱中するあまり、お父さん・お母さんがイライラしながら教えるのはお子さんにとってよくないですよね。
小さいお子さんの勉強で大切なのはお子さん自身が興味をもって楽しめることから始めること。それには、お父さん・お母さんも一緒になって楽しむことが一番です。
たとえばひらがなの勉強では親子で一緒に絵本を読んだり、パズルやつみきなどを使って遊びながら覚えてみるなど、お子さんがどんなことに興味を持っているかをお父さん・お母さんが見極めて教材を選んであげましょう。
以上が、お子さんを勉強嫌いにさせないために気をつけておきたいことでした。
まだまだ自粛期間は続きそうですが、この機会にできることから始めてみてくださいね。