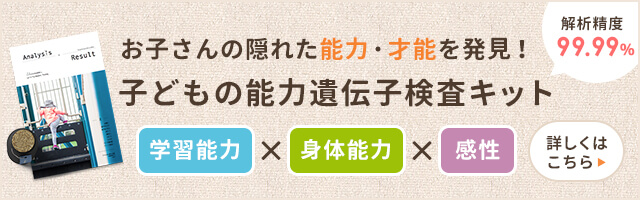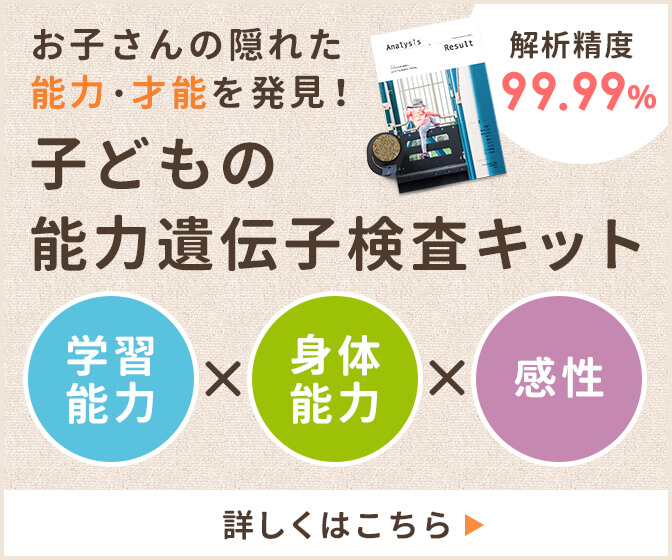こんにちは!遺伝子ママです。
お子さんが幼稚園や小学校に通うようになると、これまでお父さん・お母さんなどの家族が中心だった世界から一気に広がり、クラスでたくさんのお友だちと関わる機会が多くなりますよね。
しかし人間関係が広がるということはトラブルも増えてしまうということ。お友だちの輪に入れなかったり、すぐケンカしてしまったり「うちの子の協調性って大丈夫かな?」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
そもそも協調性とは、異なった環境や立場にいる「複数の人」が互いに助け合ったり譲り合ったりできる素質のこと。
この協調性は大人になるにつれて「社会性」となり、生活をしていくうえで大切な人間関係を作るための基礎となっていくものなので、お子さんの協調性が見についていないと不安になってしまいますよね。
そこで今回は、お子さんの協調性を伸ばすためにどうしたらいいのかまとめてみました。
親としてどんなサポートをしてあげたらいいんだろう?と思っていた方は参考にしてみてくださいね。
協調性はいつから育つ?

一般的にお子さんは3歳くらいからじょじょにお互いを意識しだし、小学生ごろまでに「協調性」を身に着けていきます。
よく「幼稚園の頃はみんなと仲が良かったのに、大きくなるとうまくいかなくて…」という方がいますが、実は幼稚園のお子さんはみんな仲良しのように見えて、たまたま趣味が合ったとか、同じ遊びがしたかっただけでまだ友達という認識があいまいなんですね。
他の人をしっかり意識できるようになるのは5歳から6歳ごろにかけて。このころに友達を思いやる気持ちや、一緒に遊ぶことの大切さを教えることが協調性を育てるために大切なことになります。
つまり、幼稚園のお子さんはまさに協調性を育んでいる真っ最中ということ。お友だちの輪に入れなかったり、ケンカしてしまったりはお子さんの心の成長のために大切なことともいえるでしょう。
だけど、やはり親としては余計なトラブルは避けたいですよね。では次にお子さんが協調性を身につけるためにどうしたらいいかコツをご紹介します。
協調性を身につけるには

お友だちの輪に入る手助けをする
お子さんの性格によっては、なかなか自分から友達の輪に入れないこともあるでしょう。そんなときはお父さん・お母さんからうまく声かけをして友達の輪に入る手助けをしてあげるといいですね。
もちろん、お子さんが嫌がっているのに無理やり友達の輪に入れようとするのはよくありませんので、お子さんが嫌がっているかどうかはお父さん・お母さんが判断してあげましょう。
そしてお子さんが友達の輪になじんだと思ったらそっと輪から抜けて見守ってあげてください。
相手の気持ちを考えさせる
協調性を育むには、自分の気持ちを優先するだけでなく相手の気持ちを考えさせることがとても大切です。
たとえばお子さんがお友だちとケンカをしてしまったときは、お子さんの気持ちを受け止めてあげたあとに「どうして○○ちゃんは意地悪したのかな?」と相手の気持ちを考えてみる練習をさせてあげましょう。
ここでは、まずお子さんの話をしっかり聞いてあげることが大前提。お子さんは自分の話を聞いてもらえたことで、お父さん・お母さんからの話もスムーズに聞けるようになります。
お友だちとのトラブルがあったときには、お友だちの気持ちを考える練習をすることで、お子さん自身も柔軟な考え方ができるようになるでしょう。
集団行動のルールを教える
私たちが社会で生活していくためにはルールやきまりを守る必要がありますよね。それはお子さんも同じこと、みんなが楽しく遊べるためのルールや集団での役割をしっかり教えてあげましょう。
ルールをしっかり覚えられるようになったら、今度は周りをよく見てルールを守れないお友だちを注意したり、教えたりもできるようになります。
集団行動での立ち位置やルールを学ぶことは、幼稚園だけでなくこれからの生活でも必ず必要になってきますので、お子さんの協調性を育むために教えたルールは必ず守る約束をすると良いですね。
以上が協調性を身に着けるためのコツでした。
これらは幼稚園だけでも身に着けることができますが、もっと早く協調性を身につけたいという方は習い事を始めるのも良いでしょう。
学校以外にコミュニティを作ってあげるのはお子さんにとっても良いことですし、習い事では同年代だけではなく幅広い年代の人と交流することもできます。
では協調性が身に着く習い事はどのようなものがあるのでしょうか?
協調性が身に着く習い事!

スイミング・体操
お子さんの習い事として人気のスイミング・体操は、比較的低年齢のお子さんでも始めることができ、運動の基礎を身に着けることができます。
個人競技のように思われがちですが、ほとんどのスクールは集団での指導が多く、道具やレーンを順番に使用するため集団行動が必須です。
また水中での競技や全身の柔軟性を使った運動ということもあり、先生の指導をしっかり聞かないと危険な競技でもあるので、人の話を聞く習慣を身に着けることができるでしょう。
サッカー・野球などのチームスポーツ
サッカー・野球・バスケットボールなどチーム戦で行うスポーツは、練習・試合どちらでも常に協力し合うことが大切なのでかなりのコミュニケーション能力や協調性が身に付きます。
チーム戦では集団の中で自分がどう動くべきなのかを考えながらプレイしますし、自分だけのペースに合わせてくれるわけではないので、集団の中での立ち位置やルールを覚えるにも最適です。
その他にも早起きやあいさつ、準備、片付けなど基本的な常識も合わせて学ぶことができるので、親子で学べることは多いでしょう。
リトミック
激しい運動が苦手なお子さんには、音に合わせて動くことで表現力や思考力の基礎を学ぶリトミックもおすすめです。
リトミックはグループで行う習い事なので、一緒にレッスンを受けているお友だちがうまく合わせられなかったときや自分がうまくいかなかったときなど、お互い助け合うことで協調性を育むことができるでしょう。
リトミックもスイミング・体操のように比較的低年齢から始められ、室内で行える習い事です。また全身だけでなく耳や目から受け取った情報をもとに進めるので、発達途中のお子さんの脳にとても良い刺激になるでしょう。
今後ピアノや音楽を習わせたいという方には、音楽教育の基礎としてリトミックが最適です。
以上が、お子さんの協調性を育むための習い事でした。
もちろん協調性が高いこと=優れた子というわけではありませんし、お子さんの協調性には個人差があるので、あまり無理やり協調性を伸ばそうとする必要はありません。
しかし成長していくうえで切り離せない集団行動をスムーズに行うためにも、お子さんが身につけられる範囲で協調性を育ててあげましょう。